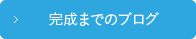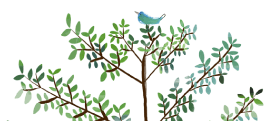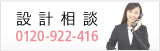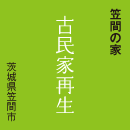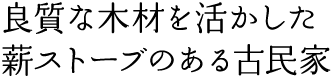設計から施工まで約3年がかりで完成しました。建物は今から121年前となります、明治28年(1895年)2月に、施主の曽祖父によって建てられました。
敷地は、古くからの集落内に位置していますが、現在では古民家は5軒ほどしか残っていません。間取りは、多室型整形6間取り、瓦葺き入母屋屋根のせがい造り。昭和40年代に屋根を茅葺から、現在の瓦葺へ葺き替えています。その際に寄棟から入母屋屋根に大改造をしたものと思います。
調査を行い、柱や梁、桁の主要な木材が良質なことと、その仕口や継ぎ手の巧妙さに驚くばかりでした。その為に、東日本大震災でも目立った被害はありませんでした。これまでも何度かリフォームはされていましたが、将来を見据えた大々的な再生の依頼を受けて設計がスタートしました。
建物は一度壁を取り払い、地上1.2mほどリフトアップした状態で基礎を作り、新たな土台を敷きその上に建物をおろしました。メイン構造と外観の意匠は、当時の状態を保ちつつ、これからの住まいとして必要な機能性の確保、温熱環境や耐震補強などを提案いたしました。
間取りは、奥座敷と手前の和室は残し(復元)、その他は大黒柱や差し鴨居、梁を活かしながら、キッチンやダイニングを中心とした開放的でのびのびとした空間と、家族それぞれがプライベートも楽しめる個室空間とメリハリのある構成としました。大きな空間を温めるために、施主のご要望であったヨツール社の薪ストーブを設置しました。また、玄関を一歩中へ入ると、黒いチョウナ削りの梁が見える吹き抜けの土間空間が、この家のシンボルとしてお客様を出迎えます。