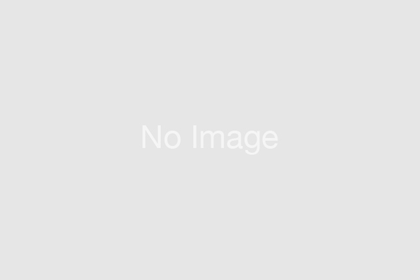2025-04-04
「北欧のあかり展」を見てきました。
日本橋高島屋で開催されていました「北欧のあかり展」を見てきました。6年前にフィンランドを旅したことを追体験しながら見て回りました。首都のヘルシンキ市内を散策しながら感じたのが、日本でゆう夕方の時間がとても長く、その時間帯を楽しむ文化(ヒュッゲな暮らし)が根付いているなと思った事です。それをブルーアワーと呼ぶことを今回知ることが出来ました。そうした歴史と文化の中で街や建築と調和する灯が生み出され、現在まで質の高い照明器具が作られていることを理解しました。
展示会では、100年の間に北欧で誕生した約100点の名作照明器具とそのデザイナーを紹介していました。また、照明器具の実物の展示に加えて、他のインテリアと併せて部屋としての設えがあり、より生活の中での灯をイメージできました。本展を企画した小泉隆さんは、近代照明の父と呼ばれるポール・ヘニングセンが残した「夜は昼にはならない。」というメッセージを大事にしされていてい、入口に北欧のノスタルジックな暮らしの風景が展示されていました。
住宅設計をしていて最近は、シンプルな暮らし方への志向が強い事や、LEDライトの進化などもあり空間を邪魔しない、ダウンライトや間接照明を使用する機会が多いのですが、改めて美しい照明器具(灯)の存在が建築そのものと、そこで過ごす時間の双方の質を高める事に繋がる事を感じました。

暗さを良しとして、必要な場所にキャンドルを灯す感覚で照明器具を配置しています
。




①完全にグレア(眩しさ)を取り除くこと(グレアフリー)
②必要な場所に適切に光を導くこと
③用途や雰囲気作りに応じて、適切な色の光を用いること




関連記事